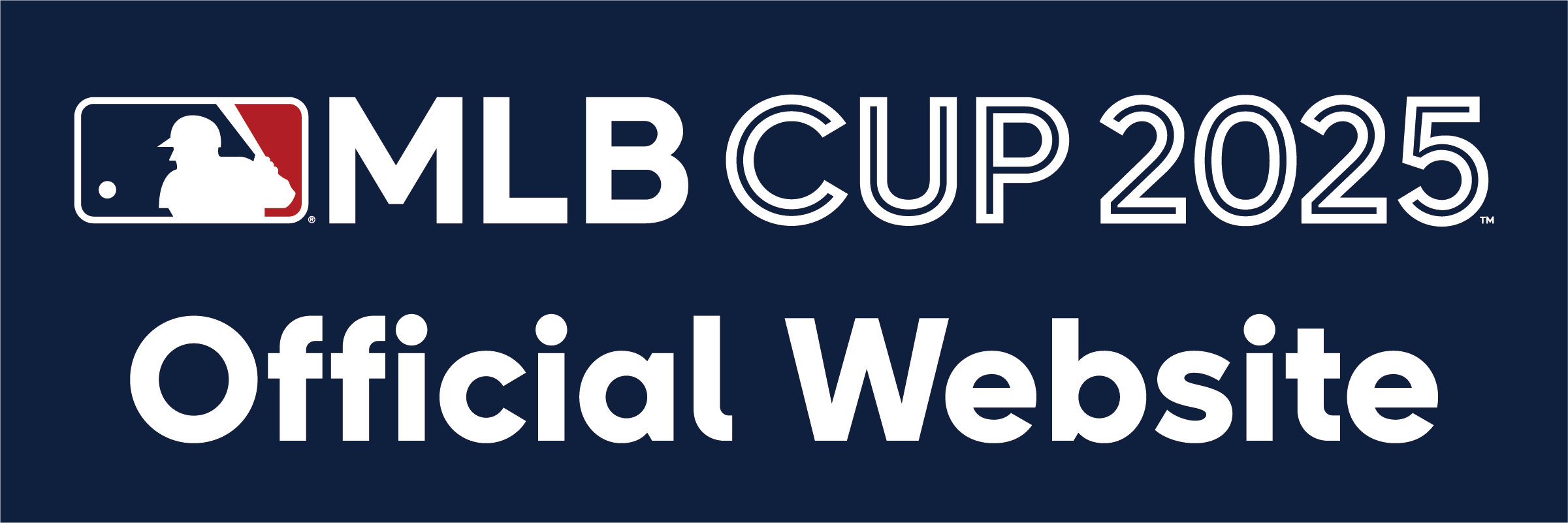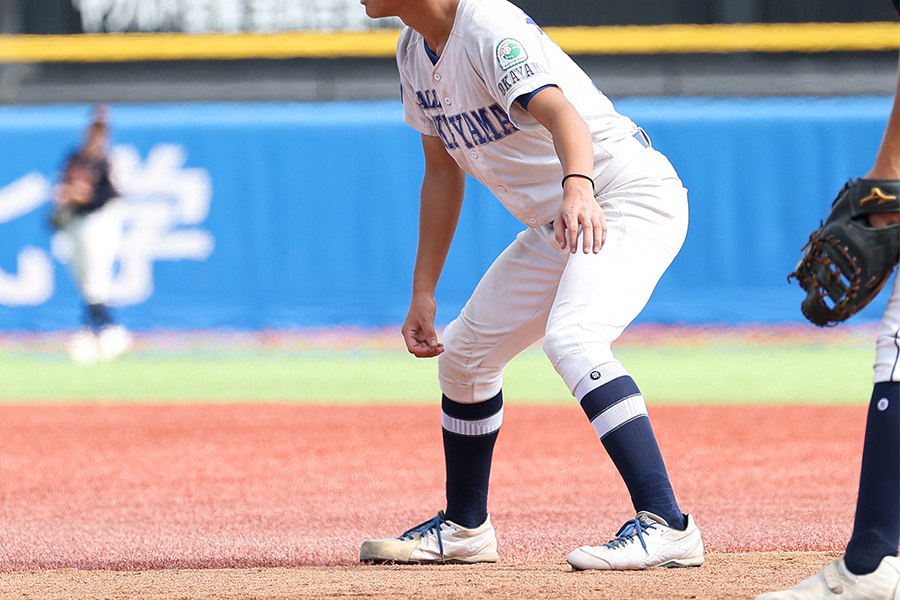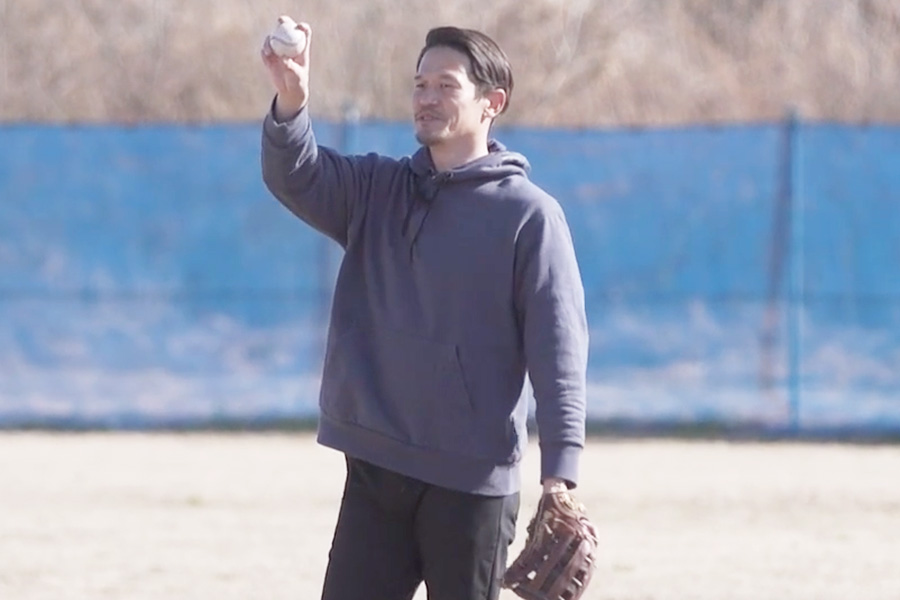審判を守るため…徳島県軟連は2025年度から全カテゴリーの試合に“リクエスト”を導入
子どもたちの野球離れを防ぐと同時に「審判を守るために」と、徳島県軟式野球連盟は今年度から「協議(リクエスト)」制度を導入している。全日本軟式野球連盟の下部組織では全国初の試みで、対象は学童からクラブチームを含む大人までの全カテゴリー。「一瞬の判断に加えて審判団が協議することで判定の正確性が高まる」「判定が覆らなかったとしても心のわだかまりが消える」と、チーム関係者や選手から歓迎されている。
この制度は、プレー中の判定(アウト・セーフのみ)について、他の審判員や観客から見て誤審の疑いがある場合に、監督から「協議」を申し出ることができるというもの。ビデオでの確認はなく、審判員4人がマウンド付近で話し合い、球審が結果をベンチに伝える。失敗の場合はその1回限り、成功の場合は何度でも申し出ができる。
導入を決断した同連盟の十川佳久会長は、「野球人口の減少がよく言われ、私もそれをすごく感じます。審判も同じです。プレーする人だけじゃなく、審判もいないと野球はできないでしょう」と語る。練習試合の審判ならばチーム関係者が担ってもいいが、公式戦となれば公平性を保つためにチームから独立し、ルールを熟知した審判団が必要になる。
しかし、全国的に審判員は減少傾向。興味を持つ人材が少ないことが最大の原因に挙げられるが、その他に、判定を不服とする選手に悪態をつかれたり指導者の怒鳴り声を浴びたりすることで、やりがいを見失い、“実働なき審判員”になってしまうケースもある。
SNS時代の昨今は、疑惑の判定を下した審判として名指しされ、写真や動画を用いてネット上で非難されることで心が壊れる事態も発生している。審判員不足、審判員の高齢化に直面している同連盟が「協議(リクエスト)」の導入を決めたきっかけもSNSの誹謗中傷だった。
きっかけは審判員を非難するSNS投稿「誰が絶対という時代ではない」

「プレーの写真と判定を批判する文章が昨年、SNSに投稿されて、その試合に全く関係のない人までコメントを寄せて、炎上状態になったんです。試合中に抗議はありませんでした。たくさんの酷い言葉をその試合の審判も見たようです。どこの誰か分からない人から誹謗中傷されるって、(当事者にとって)とんでもなく恐ろしいことですよ」
真剣に野球に向き合う同連盟審判団に対する十川会長の信頼は当然ながら大きい。SNSに投稿されたジャッジは、撮影者がいる位置からは際どいプレーのように見えるが、「(審判員の目線である)真横から見れば、誤審でないことは確かです」と断言。しかし、すぐに「審判が絶対とは言いません」と言葉を続ける。
「リクエストによって判定が変わることもあると思います。それでも、誰かが、誰かを、責めるべきじゃないんです。選手、指導者、審判、“野球をする人”全員がスキルを磨き続けないといけませんし、それに終わりはありません。みんなで尊重し、話し合いながら試合を進行せねばならない。昔のように『誰が絶対』と言う時代では、今はないんですよ」
ベンチにいる指導者と審判員の双方が「協議(リクエスト)」を介し、判定に納得しながら試合をすることができれば、第三者による攻撃があったとしても、判定を下した審判員の心を守ることができる。全国に先駆けたルール改変にはそんな期待が込められていた。
少年野球の現場を熟知するコーチが参加…無料登録で指導・育成動画250本以上が見放題
野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」(ターニングポイント)では、無料登録だけでも250本以上の指導・育成動画が見放題。First-Pitchと連動し、小・中学生の育成年代を熟知する指導者や、元プロ野球選手、トップ選手を育成した指導者が、最先端の理論などをもとにした、合理的かつ確実に上達する独自の練習法・考え方を紹介しています。
■専門家70人以上が参戦「TURNING POINT」とは?
■TURNING POINTへの無料登録はこちら