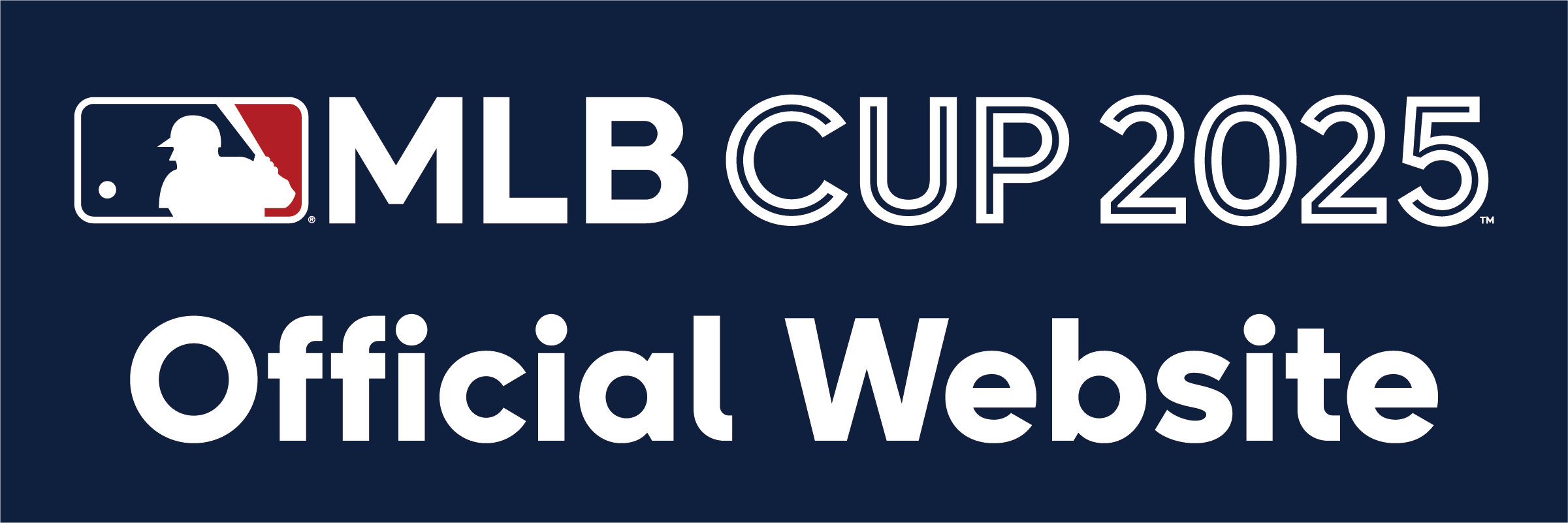2006年夏の甲子園で優勝…早実の主将・後藤貴司氏が語る送球の基本
野球の守備において基本であるスローイング。強くて正確な送球はレギュラー奪取に不可欠だが、中学生までに習得できていない選手が多い傾向にある。2006年夏の甲子園で優勝した早実(西東京)で主将を務め、現在、少年野球の指導にも関わっている後藤貴司氏は「高校入学前にスローイングを完璧にしておくことは大前提です」と力を込める。
「本来は小学生のうちにやっておくべきことです。少なくとも中学生のうちには、ある程度固めておかないといけません。高校に入った後に、スローイングが確立できていない選手は結構多いんです。ノックや実戦で、上体がキャッチボールと同じ動きができなくて、苦しむことになります」
上半身の動きで注目するのは両肩。送球の際、トップの位置では右利きの選手は左肩が送球方向を向き、右肩は水平に真後ろにくる。そこから体を回転させてリリースの瞬間に両肩は水平のままで、送球方向と正対するのが理想の形である。
「目標に対して肩のラインを90度にする。それって誰でも当たり前だと思うじゃないですか。でも、高校生でもできていない選手が結構いるんですよ。体が開いてしまったり、一方の肩が下がったりしている。そうなると、悪送球につながる可能性がかなり高くなります」
キャッチボールは「実験」「遊びながら道具を扱う感覚を養う」

ステップする足も目標に真っすぐ踏み出す必要がある。習得するにはキャッチボールから強く意識すること。「投球練習が一番いい」という後藤氏は「短い距離で投げたり、逆に長めの塁間の距離で投球してみる。テークバックを大きくしたり、野手のように小さくしたり、いろんなパターンを試していくと感覚をつかめるようになると思います」と提案した。
自身は小中学生時代「壁が相手でした」と振り返る。「“壁当て”ができる環境だったので、目標に向かってどう投げるか考えながら練習していました。近くから投げたり、遠くから投げたりして感覚をつかみました。守備の練習にもなるから、壁当ては一番いい練習かなと思います」。跳ね返りを捕球するのも、さまざまなゴロの変化があって守備の上達につながるのである。
近年は練習場が限られ、壁当てができない選手も多いだろう。その場合はキャッチボールで工夫するしかない。「コントロールは指先の感覚が重要です。上から投げたり、ちょっと横から投げたりしながら、ちゃんと相手の胸にコントロールします」。ランニングスローを織り交ぜたり、球の握り方をあえて変えることもあるという。
「キャッチボールは実験のような感覚でやるといいと思います。どんな力感だとボールに力が伝わるのか、失速するのか、試しながら投げるんです。必ずしも硬式球じゃなくていい。軟式でも、軽いカラーボールでもいい。遊びながら道具を扱う感覚を養って自分のイメージに近づけていく実験だと思います」。漠然と投げるのではなく、常に意識しながら練習する。時には遊び感覚も必要。試行錯誤しながら、引き出しを増やしていくのである。
甲子園常連の名門校出身者も参加…無料登録で指導・育成動画250本以上が見放題
大阪桐蔭元主将の廣畑実さん、水本弦さんら名門高校出身者も参加する野球育成技術向上プログラム「TURNING POINT」(ターニングポイント)では、無料登録だけでも250本以上の指導・育成動画が見放題。First-Pitchと連動し、少年野球を熟知するコーチや、元プロ野球選手、トップ選手を育成した指導者が、最先端の理論などをもとにした確実に上達する独自の練習法・考え方を紹介しています。
■専門家70人以上が参戦「TURNING POINT」とは?
■TURNING POINTへの無料登録はこちら